介護と仕事の両立をまずは考える
高齢者人口が増加している中、少子高齢化、介護保険制度の改正、社会保障の問題など、家族介護が必要になると、家族としてどのように介護を担っていくかが大きな問題となっています。その中に、介護離職も問題のひとつとして、年々深刻化しています。
親など家族が要介護状態になると、働いている家族にとっては、仕事と介護の両立に悩むのです。仕事と介護の両立が困難になると、やはり仕事をセーブしたり、介護のために離職するケースも増えているというのが実情です。中には介護離職により、生活自体が困窮し、生活保護など国の支援に頼る家庭も増えています。

介護離職する前に、まずは、介護制度の仕組みや介護休業などを理解し、第三者の手を借りながら支援を受けることを前提として考えていきましょう。そして、介護離職をするためには、ある程度の『介護に集中する期間』を設け、期限を決めることです。または、会社で介護休業が取れるのであれば、有給と介護休暇を合わせて取得するなど、介護者が社会から完全に離れることがないように考えていきます。
なぜなら、介護離職者は40代~50代の世代が多く、一度退職をしてしまうと、年齢的にもなかなか復帰は困難になります。資格などを持ち、年齢関係なく働いていける方であれば別ですが、大体はどこの企業も年齢的なことを考慮して採用をしている所が多く、そのためにも自分の置かれている状況の中で退職をしたとしても、社会復帰は難しいかもしれないということを想定して、介護生活をどうすればいいのかを考えていきます。
介護離職に至るケース
介護自体は休みなく続くものです。家族の介護度が上がり、認知症などによる徘徊や目が離せない状況になると、仕事どころではなくなってきます。仕事中に家族に何があるかわからないなどの状況に置かれると、
『仕事を辞めて介護に専念した方がいいのではないだろうか?』
と思いが出てきます。介護保険を利用するまでではない、と考える方もいるようです。また、ご本人が介護保険を利用することに難色を示し、介護保険を利用できない状況になる家庭もあります。そうなると家族間で介護を担うしか方法が無くなり、介護のための離職を考えるようになります。
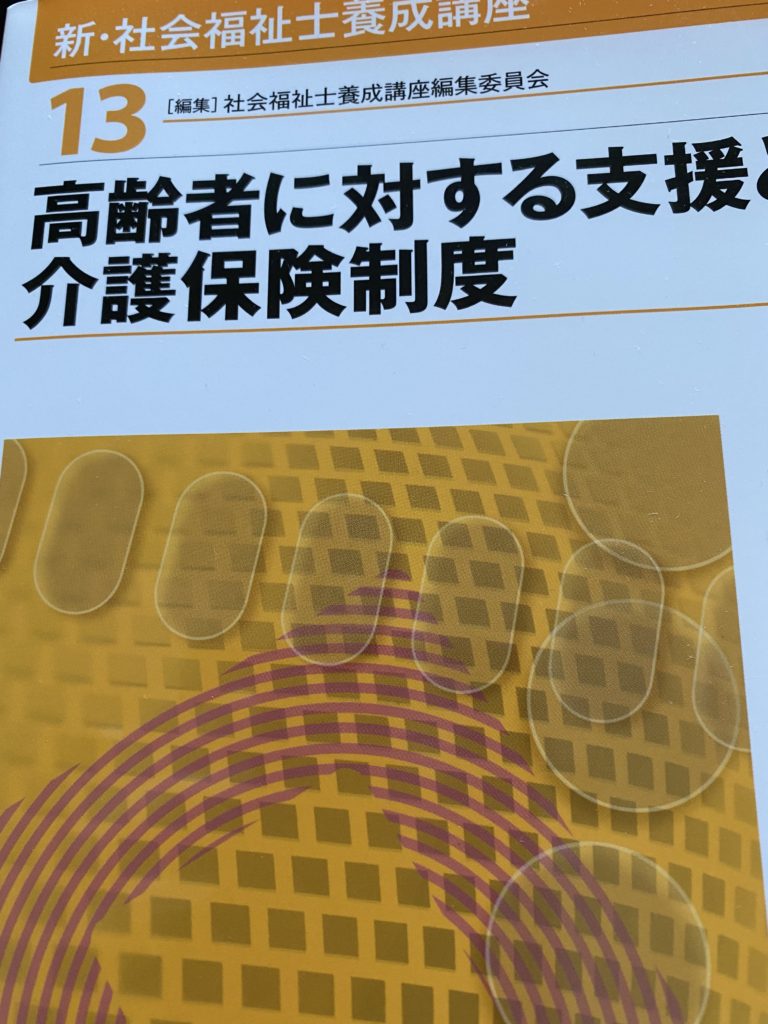
私はシングルマザーで子育てをしながら、母の介護をしてきました。母も父も当初は介護保険を利用することには否定的で、
『家族間でどうにかなる。人の手を借りることは恥ずかしい』
と言う考えでした。当時介護の仕事をしていた私は、何年かかけて両親に介護保険の大切さを話していきました。両親の考えが変わったのは、介護者である父が倒れたことがきっかけです。その時に私しか母の介護を担う人がいなく、ましてや仕事と子育てに奮闘している時期に、父はさすがに私だけに母を託して入院するわけにはいかなくなったのです。母はそれでも拒否し続けました。でも、父の説得でしぶしぶ介護保険の利用をすることに同意したのです。その時すでに母は要介護3でした。
当時は母からは
『仕事を辞めてお父さんの世話と家事と私の世話をしてほしい。給料は出すから』
と、再三言われていました。父は自営業をしており、母は今までずっと自宅で父の会社の事務をしていたこともあり、それを私に担わせようとしていたのです。自宅で事務の仕事をしながら母の介護をするということが、母の理想でした。一時母の意思を組んで、父の会社の事務をしながら母の介護と育児をしていましたが、全く社会から孤立したような気分になり、四六時中家族と顔を突き合わせて、子育てにもダメ出しをしてくる母との関係にストレスがたまり、鬱になってしまったのです。
その後、療養を経て、外で働くことを選択し、母と距離を置きましたが、仕事中や明け方など時間に関係なくひっきりなしに母からかかってくる電話に、
『やはり仕事を辞めて介護に専念した方がいいのでは?』
と思うようになりました。
介護が生活の中心となると心休まる時間はあません。でも、ようやく介護保険を利用できるようになると、ヘルパーや訪問看護、訪問リハなどの支援者が来てくれることで気持ちはかなり楽になりましたが、母の場合はそれでも、何かあると仕事中でも関係なく
『ヘルパーさんには頼めないことがあるから帰って来て』
と連絡が来ました。帰ってみると、箪笥の整理をしたいとか、買い物に行ってほしいとか、今すぐしなくてもいいような用事のために私を呼びつけることも多かったのです。その時も
『ヘルパーが来ても私がやらなければならないことは変わらない気がする。やっぱり仕事をやめた方がいいのでは?』
と思い続けていました。結局母は途中から施設入所や入院をすることになり、在宅介護は外泊の時しかなくなりましたが、それでも家族負担は大きく、事あるごとに母から呼び出されます。その時ようやく気付きました。
介護離職と言う選択をしてもしなくても負担は変わらない、ならば、離職しない方が自分と家族のためだ
と思えるようになったのです。自分の気持ちをシフトし、自分の生活を守ることを優先としたのです。
企業の介護休業制度
介護休暇と言う制度は今やどこの企業にもあります。どのような制度なのでしょうか?
〇介護休業の概要
原則として「要介護状態」の家族を介護する会社員などは、育児・介護休業法に基づき、「介護休業」を取得することができます。
【要介護状態】 負傷、疾病などにより2週間以上にわたり、常時介護を必要とする状態。
【対象になる家族】 配偶者(内縁含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、になる。
【休業できる期間】 対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに3回を上限として通算93日まで。
【手続き】 休業開始予定日と、休業終了予定日を決めて、原則として2週間前までに、書面等により会社側に申し出る必要がある。
【給付金】 介護休業を取得した雇用保険の被保険者(65歳未満の一般被保険者、65歳以上の高年齢被保険者)は原則、「介護休業給付金」を受給できます。給付額は原則として、休業開始前の給与水準の67%です。
ただし、休業中に給与(介護休業の期間を対象とする分)が支払われた場合、給付金は減額・または不支給となる場合もあります。介護休業給付金には、上限額および下限額が決められています。また、同一の対象家族について、介護休業給付金を受けたことがある場合でも、異なる要介護状態で再び介護休業を取得したときには介護給付金を受給できます。ただし、同一の対象家族について受給できる日数は通算93日までです。

介護休業と言う制度はまだまだ浸透していない企業も多くあり、介護休業を取得したいと伝えても、戻って来ても席はない、などと言われたというケースもあります。会社での立場や、逆に休業することで、自分自身が会社に対して負い目を感じて結果退職するというケースもなくはありませんが、利用できるのであれば、まずは介護休業という制度を利用しながら家族間で今後の生活の基盤を整えることも一つの方法です。
その他の介護に関わる制度
厚生労働省の資料では、「介護に直面しても仕事を続ける」という意識が重要としています。
誰にも相談せずに介護離職してしまい、経済的、精神的、肉体的により追い込まれてしまうこともあるからです。
先にも書きましたが、通算93日と言う機関の介護休業ですが、「自分が介護を行う期間」というよりは、「今後、仕事と介護を両立するために体制を整えるための期間」と捉え、有効に活用することが今後の生活スタイルを考えるためにも大切な期間でもあると思います。
地域包括支援センター(高齢者の生活を支えるための総合機関として各市町村が設置)や、ケアマネジャー(介護支援専門員)などと相談しながら、介護保険のサービスを上手に利用しましょう。
〇介護休暇
要介護状態にある家族が1人の場合は、年5日、2人以上の場合は年10日を上限として、時間単位から取得できます。
〇勤務時間短縮等の措置
要介護状態にある対象家族1人につき介護休業とは別に、利用開始から3年以上の間で勤務時間の短縮の措置を2回以上利用が可能とするなど、会社側は以下のうち少くとも1つの措置を講じなければなりません。
(短時間勤務のほか、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、介護サービスの費用の助成)
〇法廷時間外労働の制限
介護者が申し出た場合には原則、会社側は所定労働時間を超えて労働させることができません。また、申し出がある場合は1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。
〇深夜業の制限
介護者が申し出た場合には、会社側は、深夜(午後10時~午前5時)に労働させてはいけません。

これらは労働基準法に定められている制度で、介護においてでもこれらの制度を利用する権利はあるのです。利用できる制度を駆使して、社会から孤立することのないような生活を模索していくことが長く介護を続ける秘訣とも言えるでしょう。
介護離職をする前に出来ることを
介護離職をする前に先にかいたような制度を利用しながら、今後の生活を整えることはとても大切な事だということを再度確認してほしいと思います。
それでもやはり介護離職を考えたいのであれば、年齢的なものやキャリア等様々なことを踏まえて再就職できるかの趣味レーションや情報を集めることをお勧めします。また、離職期間が長ければ長いほど時間も年齢も重ねていくことで、再就職は困難を極めると思っておいた方がいいかもしれません。
厚生労働省も介護離職をせずに介護を続けられるための相談窓口などを紹介しています。とはいえ、制度を利用するにはそれなりの限度があるかもしれません。
正社員としては働くことが困難な場合は、パートやアルバイトと生活保護で生活をしている、というケースもあるのです。このような生活がずっと続くわけではないと割り切って生活保護を申請しているという方もいます。
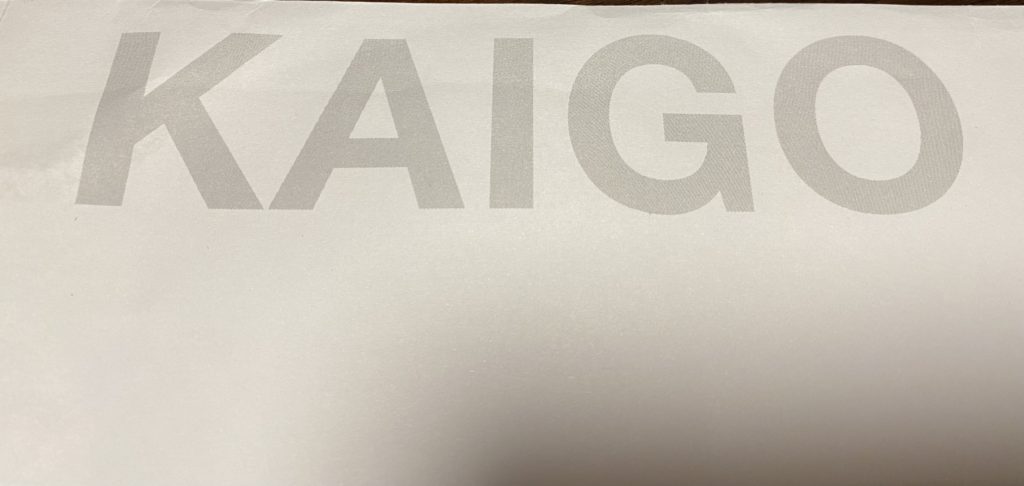
何をするにも経済的な問題が第一となります。生活保護をもらうことに躊躇する方もいますが、しばらくの間と期限を決めてでも、生活を成り立たせることも必要になるかもしれないということも考えておくことです。
介護のために仕事を辞めるか辞めないかの選択は、あくまでもその家庭の事情にもよりますが、社会と離れることで、逆に介護にも支障をきたし、虐待や貧困などに繋がることもあるのです。介護保険や介護休業等、利用できる制度を利用しながら、生活の基盤を整え様々な手を借りながら、お互いに安心して介護が出来る環境を作っていきましょう。






